
| 2005.4 | |
|---|---|
 |
|
| ack-ack’通信 | |
今は昔・・・30年前? 写真は昨年、赤坂プリンスホテルで催された「笈田敏夫・思いで語りの会」 で上映したスライドの1P(Wellcome~37P・37枚/本編100P・180枚、未使用も含め写真250枚程をスキャン!)で、懐かしいユーケントスなのです。ボスに寄っ掛かかられている上原オーナー(現・仁舜庵)に、生誕80年記念ビデオコンサートの会場で、「オヤジが丁度50の時、ウチでのライブを始めたんですよ。」と伺う。「そっか~、今の俺より10以上も若かったんだ。」と妙な納得をしつつ、もっと昔の事が鮮明に思い起こされた。鈴木章治とリズムエース在籍時、ボスも一緒に大阪へビータ(旅)。ドでかいキャバレーでビリー・ボーンOrと2バンドで昼夜2本分のステージをこなして半年後?たまたま、同じメンツでの仕事があり、ボスとその時の話で大いに盛り上がったのだが、「そういゃ~、アレ、引っ掛かっちゃって、参ってんだよなぁ~。(ギャラ!)」、「そうなんですってね。我々は章治さんから頂けましたが大変でしたよね。」、「・・・エッ、章ちゃんもそうなの?そりゃ~、嬉しいこと聞くねぇ~。なんか、こう、パ~ッと明るくなっちゃったなぁ~。」。そこへ入って来た章治さんに大きな声で「ネッネッ、章ちゃんもなんだってねぇ~。どうせ、俺だけなんだろうと、落ち込んじゃってたから、嬉しくなっちゃってさぁ~。良かった、良かった!」、「エ~ッ、ゲソちゃんもなの?そっちはてっきり貰ってる思ってた・・・、ちっとも、良かないよ。こっちは他にメンバーだって居るんだからさぁ~。」、「そりゃぁ~、そうだよなぁ~。大変だわなぁ~ウン?!?」。今思いますには、昨日の会話だとしても、同じような展開になる気がしないでも・・? で上映したスライドの1P(Wellcome~37P・37枚/本編100P・180枚、未使用も含め写真250枚程をスキャン!)で、懐かしいユーケントスなのです。ボスに寄っ掛かかられている上原オーナー(現・仁舜庵)に、生誕80年記念ビデオコンサートの会場で、「オヤジが丁度50の時、ウチでのライブを始めたんですよ。」と伺う。「そっか~、今の俺より10以上も若かったんだ。」と妙な納得をしつつ、もっと昔の事が鮮明に思い起こされた。鈴木章治とリズムエース在籍時、ボスも一緒に大阪へビータ(旅)。ドでかいキャバレーでビリー・ボーンOrと2バンドで昼夜2本分のステージをこなして半年後?たまたま、同じメンツでの仕事があり、ボスとその時の話で大いに盛り上がったのだが、「そういゃ~、アレ、引っ掛かっちゃって、参ってんだよなぁ~。(ギャラ!)」、「そうなんですってね。我々は章治さんから頂けましたが大変でしたよね。」、「・・・エッ、章ちゃんもそうなの?そりゃ~、嬉しいこと聞くねぇ~。なんか、こう、パ~ッと明るくなっちゃったなぁ~。」。そこへ入って来た章治さんに大きな声で「ネッネッ、章ちゃんもなんだってねぇ~。どうせ、俺だけなんだろうと、落ち込んじゃってたから、嬉しくなっちゃってさぁ~。良かった、良かった!」、「エ~ッ、ゲソちゃんもなの?そっちはてっきり貰ってる思ってた・・・、ちっとも、良かないよ。こっちは他にメンバーだって居るんだからさぁ~。」、「そりゃぁ~、そうだよなぁ~。大変だわなぁ~ウン?!?」。今思いますには、昨日の会話だとしても、同じような展開になる気がしないでも・・?(左下 35歳位の小生?+植松孝夫、福井五十雄/右上 故・千葉ちゃん、麻生ちゃん) |
|
読者のホーム・ページ(92) よっぱライフプランナー 4月、新入学の季節である。何らかのクラブに入部し、クラブ活動に精を出す人もいることだろう。今回は、私のクラブ活動に関するひとつの汚点?の話をさせて頂こう。私はスポーツではラグビーが一番好きである。何故なら、ずっと自分でプレーしていたから。今から33年前、私は大阪の中学校へ入学し、ラグビーに出会うことになる(大阪は中学ラグビーが盛んで殆どの中学校にラグビー部があった)。迷った挙げ句、何故かバスケットボール部に入部した私は、隣でグラウンドを走り回るラグビー部を見て惹かれていった。顧問の先生が引き止めるのを振り切り、6月にはラグビー部に移ってしまった。その時、ラグビーやろうよと誘ってくれたのが同じクラスの竹村君で、彼はその後、強豪の高校・大学でプレーし、トヨタ自動車でTVにも映る位の選手になった。中学卒業までラグビーを続けた私は、地元の公立高校に入学し、当然ラグビー部に入部した。この高校は、進学校でありながらラグビー部も古豪であり、何度か大阪代表として全国大会に出場したことがあった。同じ中学からも同級生や先輩も何人か入部しており、私はやる気満々であった。練習はハードであり、受験勉強で身体のなまった私には特にきつかった。よろけながらも自転車で帰宅し、持ち帰ったラグビーボールを出ない唾で磨き(当時、ラグビーボールは革製であり、唾で磨くと一番光った)、学校の宿題をしながら寝てしまうという毎日が続いた。入部して数ヶ月が経った頃、学校で私の自転車が盗まれるという事件が起こった。仕方なくもう1台の自転車で通学していたが、ある日、ラグビー部のある3年生が、無断で拝借したという自転車に乗っていた。よく見ると、私の自転車ではないか。しかし、「それは私の自転車です。」と言う勇気が無く、その先輩に対する不信感だけが募っていった。その後、自転車置き場でその自転車を発見し取り戻したが、それ以来、私の気持ちは冷めていった。そして半ば逃げる様にラグビー部をやめてしまった。当時の主将が気に懸けて何度も足を運んで下さったにも拘わらず。これが、私の幾つかある汚点?のひとつであるが、やはりラグビー部をやめてしまった事は、その後ずっと後悔している。私に、もう少し図太さがあれば良かったのに。その後、私は大学でまたラグビー部に入部し、4年間ラグビーを続け、社会人になってからも38歳まで会社のラグビー部に在籍することになる(実際に試合に出場したのは33歳まで)。これも、高校時代にラグビー部をやめた苦い経験から、絶対に途中でやめまいと心に決めていたからかも知れない。その後、私は脱サラしてライフ・プランナーという職業に就いてしまったので、ラグビーへの関わりは薄くなってしまった。しかし、あれ以来、私の好きな言葉は「継続は力なり」となっている。30年前のことを思い出してちょっとしんみりしてしまったが、こんな時はクリフォード・ブラウンの華やかなトランペットで“I
Remember April"と参りますか・・・これって決まりすぎ??そして、やはりずっと続けているバーボン。これも「継続は力なり」かな~? 4月、新入学の季節である。何らかのクラブに入部し、クラブ活動に精を出す人もいることだろう。今回は、私のクラブ活動に関するひとつの汚点?の話をさせて頂こう。私はスポーツではラグビーが一番好きである。何故なら、ずっと自分でプレーしていたから。今から33年前、私は大阪の中学校へ入学し、ラグビーに出会うことになる(大阪は中学ラグビーが盛んで殆どの中学校にラグビー部があった)。迷った挙げ句、何故かバスケットボール部に入部した私は、隣でグラウンドを走り回るラグビー部を見て惹かれていった。顧問の先生が引き止めるのを振り切り、6月にはラグビー部に移ってしまった。その時、ラグビーやろうよと誘ってくれたのが同じクラスの竹村君で、彼はその後、強豪の高校・大学でプレーし、トヨタ自動車でTVにも映る位の選手になった。中学卒業までラグビーを続けた私は、地元の公立高校に入学し、当然ラグビー部に入部した。この高校は、進学校でありながらラグビー部も古豪であり、何度か大阪代表として全国大会に出場したことがあった。同じ中学からも同級生や先輩も何人か入部しており、私はやる気満々であった。練習はハードであり、受験勉強で身体のなまった私には特にきつかった。よろけながらも自転車で帰宅し、持ち帰ったラグビーボールを出ない唾で磨き(当時、ラグビーボールは革製であり、唾で磨くと一番光った)、学校の宿題をしながら寝てしまうという毎日が続いた。入部して数ヶ月が経った頃、学校で私の自転車が盗まれるという事件が起こった。仕方なくもう1台の自転車で通学していたが、ある日、ラグビー部のある3年生が、無断で拝借したという自転車に乗っていた。よく見ると、私の自転車ではないか。しかし、「それは私の自転車です。」と言う勇気が無く、その先輩に対する不信感だけが募っていった。その後、自転車置き場でその自転車を発見し取り戻したが、それ以来、私の気持ちは冷めていった。そして半ば逃げる様にラグビー部をやめてしまった。当時の主将が気に懸けて何度も足を運んで下さったにも拘わらず。これが、私の幾つかある汚点?のひとつであるが、やはりラグビー部をやめてしまった事は、その後ずっと後悔している。私に、もう少し図太さがあれば良かったのに。その後、私は大学でまたラグビー部に入部し、4年間ラグビーを続け、社会人になってからも38歳まで会社のラグビー部に在籍することになる(実際に試合に出場したのは33歳まで)。これも、高校時代にラグビー部をやめた苦い経験から、絶対に途中でやめまいと心に決めていたからかも知れない。その後、私は脱サラしてライフ・プランナーという職業に就いてしまったので、ラグビーへの関わりは薄くなってしまった。しかし、あれ以来、私の好きな言葉は「継続は力なり」となっている。30年前のことを思い出してちょっとしんみりしてしまったが、こんな時はクリフォード・ブラウンの華やかなトランペットで“I
Remember April"と参りますか・・・これって決まりすぎ??そして、やはりずっと続けているバーボン。これも「継続は力なり」かな~? |
|
| やぶにらみ 第58回 エロールあさかわ 「差別をなくして愛ある平和な社会を築こう!」と云った言葉が選挙の時期になると聞かれるようになる。その差別とは人種差別であったり、民族、職種、男女の差別であったり、時と場合によっては意味合いが異なる。人権主義者や人権擁護団体の人達が唱える差別とは、主として身障者や日本に永住権を持った外国出身の人達を指していると思われる。しかし、差別をなくして平等の権利を主張するからには相応の義務を負わねばならない筈である。「権利と義務」のバランスが保てない限りは差別をなくすという論理は成立しない。重度の身障者に対して健康な人間と同じような義務を果たせと云っても不可能である。従って保護は与えても義務を果たせとは云わない。そこには身障者であるからと云う差別考があるからである。男女同権を声高に主張する女性知識人も多いが、男と女は肉体的にも精神的にも大きな違いがある。生まれた時から構造が違う。男は男らしく、女は女らしくすべきだと発言した男性議員が袋だたきにあった例もあるが、私は袋だたきにあった男性議員の考え方に、ある部分では賛成である。民主主義国家を自負するアメリカにも人種差別、職種、男女の差別は現存している。タクシーのドアを開けてやったり、重たい荷物を持ってやったりする行為そのものが女性は齢者であるという考えがあるからに外ならない。差別と云う言葉が不適切であると云うのであれば、「分別」、「区別」、「差分」などゴミの収集規則のような言葉に代えれば良い。元来、動物世界にも植物世界にも地球創世記の段階で、それぞれに差異差別が組み込まれている訳で、歴史の短い人間が勝手に差別をなくせなどとワメイた処で何世紀もの時間を要することになる。男女同権思想が定着するにも長時間を要するだろうが、若しそうなればセクハラなんてバカな問題も言葉もなくなる。セクハラで訴えるのは百パーセントが女性であり、「会社の帰りに先輩の女性主任に誘われて困っています。」と訴えた処で果たしてセクハラとして取り上げて貰えるかどうか。セクハラは完全に女性優位の差別である。女性社員が自分の趣味にあった上司や男性社員に誘われた場合は喜々として誘いに乗るが、嫌いな男性が声を掛けようものなら、「精神的セクハラ」を受けたと訴えるし、今まで交際していた男性が心変わりをしたと見ると、「長い間セクハラを受けました。」とのたまう。「男女、七歳にして席を同じゅうせず!」 |
|
「禁酒法とジャズ」 新 折人 #50 (2001/2~)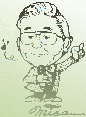 最近我が国では世の中のせいかアルコール依存症が増えていて、国会議員といえども例外ではないらしいが、アメリカでは、今から85年前の1920年、世界初、政治の力で全国的に法律をもって酒を全面的に禁止する、強引な試みが実行された。「禁酒法」(ProhibitionAct)である。この国は時折思いも掛けない行動に出る。しかし、これは結果的に悪法であった。第一に、幾ら法律で押さえても、古来人々の喜怒哀楽について廻って来たアルコールを捨てる事は出来ない。禁酒法はかえって非合法という形での酒場を増やし、その数全国で22万軒にも達した。おまけに「禁酒法」の施行は、ギャングの温床、無法世界をもたらすという皮肉な結果に帰着した。例えばこの時代のシカゴでは、アル・カポネ(1899~1947)が、密売酒で年に1億5千万ドルを稼ぎ、1,000人のガンマンを雇って我が物顔の無法世界を作り上げた。他方、皮肉な事に「禁酒法」はジャズの名曲も生んだ。1922年に出来た「シカゴ」[Chicago]という曲は、「シカゴは素晴らしいホーム・タウンだ」と歌っているが、言外に「例え禁酒法があろうとも」というフレーズを仄めかせている。何故ならこの歌詞の中に〈♪
ThattownthatBillySundaycouldnotshutdown〉(例え、ビリイ・サンデイでもシカゴを潰せない)というくだりが出て来る。このビリイ・サンデイ(1863〜1935)という人物は、元々「シカゴ・ホワイトソックス」でシーズン95個の盗塁を記録し、快足プレイヤーとしてならした大リーガーであったが、その後、何故か神がかってカリスマ的伝道者となり、禁酒運動を主導した男なのである。 最近我が国では世の中のせいかアルコール依存症が増えていて、国会議員といえども例外ではないらしいが、アメリカでは、今から85年前の1920年、世界初、政治の力で全国的に法律をもって酒を全面的に禁止する、強引な試みが実行された。「禁酒法」(ProhibitionAct)である。この国は時折思いも掛けない行動に出る。しかし、これは結果的に悪法であった。第一に、幾ら法律で押さえても、古来人々の喜怒哀楽について廻って来たアルコールを捨てる事は出来ない。禁酒法はかえって非合法という形での酒場を増やし、その数全国で22万軒にも達した。おまけに「禁酒法」の施行は、ギャングの温床、無法世界をもたらすという皮肉な結果に帰着した。例えばこの時代のシカゴでは、アル・カポネ(1899~1947)が、密売酒で年に1億5千万ドルを稼ぎ、1,000人のガンマンを雇って我が物顔の無法世界を作り上げた。他方、皮肉な事に「禁酒法」はジャズの名曲も生んだ。1922年に出来た「シカゴ」[Chicago]という曲は、「シカゴは素晴らしいホーム・タウンだ」と歌っているが、言外に「例え禁酒法があろうとも」というフレーズを仄めかせている。何故ならこの歌詞の中に〈♪
ThattownthatBillySundaycouldnotshutdown〉(例え、ビリイ・サンデイでもシカゴを潰せない)というくだりが出て来る。このビリイ・サンデイ(1863〜1935)という人物は、元々「シカゴ・ホワイトソックス」でシーズン95個の盗塁を記録し、快足プレイヤーとしてならした大リーガーであったが、その後、何故か神がかってカリスマ的伝道者となり、禁酒運動を主導した男なのである。1924年には二人でデートしてもお酒が飲めないので「二人でお茶を」[TeaforTwo]が流行った。尚、この場合の“Tea"は、その世界では「麻薬」のことを言い、意味深長である。禁酒法の間も酒を飲み続けたのであろう。1933年に出来た「ソフィスティケイテッド・レイディ」[Sophisticated Lady]の中に、〈♪ Iseeyounowsmoking, drinking never thinking of tomorrow, nonchalant・・・〉(タバコを吸い、酒を飲み、明日のことを考えようともしないノンシャラーな貴女。)という歌詞が出てくる。禁酒法が廃止されるや、早速大っぴらに酒が飲める喜びを反映して、1934年に都会風の洒落た曲、「二人のカクテル」[CocktailsforTwo]が作られた。 尚、この時代には「禁酒法」を巡る数々の俗語も出来た。気が咎めるのか、小声で注文するから「秘密酒場」のことを「スピーキージー」(Speakeasy)と呼んだ。風呂桶の中で香料とアルコールを混ぜただけの、質の悪い酒は「バスタブ・ジン」(BathtubJin)である。「密造者」は夜陰に紛れて酒を造ったので、「ムーン・シャイン」(Moonshine)という、余りそぐわない優雅な名前で呼ばれたりした。また密造酒の「運び屋」は酒を長靴の脛の部分に入れて運んだ為「ブート・レッガー」(Bootlegger)と言われた。「密造酒を飲む輩(やから)」には「スコッフロー」[Scofflaw]という言葉が与えられた。「嘲る、あざ笑う」(Scoff)と「法律」(Law)を合成した造語である。この言葉は今でも残っていて、「法律違反を度々おかす者」などの意味で使われており、辞書にも出ている。ミュージシャンの皆様、重い楽器を運ぶため車がどうしても必要なことには同情の余地がありませんが、「スコッフロー」と言われないよう、駐車違反にはくれぐれも気をつけましょう。 |
|
ルパンの私書箱~from 田舎親父 (17)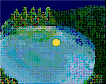 ジイサンは一発ぶっ放すと、バシャン、ボシャンとカモが水に落ちる音を聞き、そのまま家に戻る。水に入って獲物を回収するには寒すぎる。犬を使えば世話が面倒だ。戻るとカミさんが尋ねる。「アンタどうだった?」とか「獲れた?」とか・・・。「二つか三つ落ちた。水ん中だ。浮んどる。月明かりで良く見える。水は腰までもネェ、が、銃を置いてはいけネェ。持ったまんまじゃ、濡らしちまう。」、「ワシが行きましょうかネ。」となる。その夜、私がジイサンの処へ行くと、珍しくジイサンが出迎えた。「オカミサンは留守ですか?」、「あゝ、ちょいと出掛けててな、間もなく戻る。ま、上がんな。」と云いながら、奥の台所辺りから首の辺りに埃を被った様な一升瓶を抱いて戻って来る。「こいつでも、やってようじゃないか・・・。」。キヨシオジは湯飲みの縁を指先で拭いたものに、一升瓶から中のものを注意深く注ぐ。それは、白く濁っていたり、赤紫だったり、黄金色だったりする。ジュースになり損ねて、酒になっちまったという代物の一つだ。だが、こういう時刻に呼ばれるのも、オカミサンが居ないのも、オジ自らドブロクを注ぐのも変だ・・・オカシイ。呼ばれた理由に思い当たる処がある。「オジキ、私、迎えに行って来ましょう。」。「何やってやがるのか、直ぐに戻れそうなもんを・・・、ちょいと頼まれてくれるか?」、「はい、何処ですか?」、「ホンのそこだ・・・そこんとこ、イチの堤だ。カモ拾いにやった。」、「カモ拾いって・・・?」、「そう、カモ拾い・・・ワシが撃った。水ん中に落ちるだろ。この冷え込みだ、入る訳にもいかネェ。で、あれが拾いに行った。」。「オカミサンがですか?一体どうやって拾うんですか?」、「水に入らなきゃ拾えんだろう。下駄はかせたから大丈夫だ。」、「下駄って?」、「裸足じゃ怪我するだろうが・・・下駄を履かなきゃ入れん。ワシは下駄を履いてなかった。」、「ワタシ、行ってきます。」、「そうかい、頼むぜ。」私は月明かりを頼りに、休耕田の畦径を一の堤目指して急いだ。青い月明かりの下に黒々と陰の盛り上がる辺りが堤のある辺りだ。休耕田の稲の切り株には、早くも霜が輝いている。浅い池は岸辺の辺りから氷結し掛かっているかも知れない。私は自分の吐く真っ白な息の中に鼻先を突っ込みながら急いだ。池の外側の篠竹の藪の陰まで行き、呼吸を整えて耳を澄ます。藪の向こうの低い位置から、バシャンリー、バシャリーと弱い水音がする。その音は南に向かっていた。池の中に入るには水抜きの栓のある南側しかない。オカミサンはどうやら降りた所へ戻る処の様だ。私は栓口へと廻った。池の土手を上がり、藪の間から覗いて見ると、月光に輝く水面の波の中心に人影が見えた。オカミサンは片手に二羽のカモを持ち、もう一方の手で着物の裾を腰の辺り迠たくし上げている。ゆっくり、一歩一歩、下駄が抜けない様に水の中を此方へ向かって来る。「オカミサン、山口のオカミサン」。どうやら、自分が立てる水音のせいで聞こえないらしい。私は、その場を離れ、土手を下り、藪の向こうから大声を上げる。「オカミサア~ン、ヤマグチノ~!ワタシ、マチイチノ~、クニデ~ス。ムカ~イニキマシタァ!」。それから再び土手を上がり、水抜きのコンクリートを下りる。オカミサンは目の前だ。凍り付く様な水の中に腿まで浸かってやって来る。冷たさと寒さで足も動かない程の筈だ。片手にカモ、もう一方に着物の裾。「オカミサン、大丈夫ですか?」。私は思わずコンクリートの斜面を駆け降り、水辺の柔らかい砂泥に踝まで足を突っ込んで、そのまま水の中に飛び込みそうになる。「ナ、ニ、やってんだい。アブナイじゃないか。来るんじゃないヨ。」言葉の合間に歯の鳴る音がする。オカミサンは最後の力を振り絞って岸に上がり、ドサリとカモを落とした。一方の手は、まだ着物の裾をたくし上げたままだ。月明かりで青白く、濡れて光る腿がずっと上まで見えた。そして、その辺りに夜目にもそれと分かる独特の図柄が這い回っていた。
以下次号 ジイサンは一発ぶっ放すと、バシャン、ボシャンとカモが水に落ちる音を聞き、そのまま家に戻る。水に入って獲物を回収するには寒すぎる。犬を使えば世話が面倒だ。戻るとカミさんが尋ねる。「アンタどうだった?」とか「獲れた?」とか・・・。「二つか三つ落ちた。水ん中だ。浮んどる。月明かりで良く見える。水は腰までもネェ、が、銃を置いてはいけネェ。持ったまんまじゃ、濡らしちまう。」、「ワシが行きましょうかネ。」となる。その夜、私がジイサンの処へ行くと、珍しくジイサンが出迎えた。「オカミサンは留守ですか?」、「あゝ、ちょいと出掛けててな、間もなく戻る。ま、上がんな。」と云いながら、奥の台所辺りから首の辺りに埃を被った様な一升瓶を抱いて戻って来る。「こいつでも、やってようじゃないか・・・。」。キヨシオジは湯飲みの縁を指先で拭いたものに、一升瓶から中のものを注意深く注ぐ。それは、白く濁っていたり、赤紫だったり、黄金色だったりする。ジュースになり損ねて、酒になっちまったという代物の一つだ。だが、こういう時刻に呼ばれるのも、オカミサンが居ないのも、オジ自らドブロクを注ぐのも変だ・・・オカシイ。呼ばれた理由に思い当たる処がある。「オジキ、私、迎えに行って来ましょう。」。「何やってやがるのか、直ぐに戻れそうなもんを・・・、ちょいと頼まれてくれるか?」、「はい、何処ですか?」、「ホンのそこだ・・・そこんとこ、イチの堤だ。カモ拾いにやった。」、「カモ拾いって・・・?」、「そう、カモ拾い・・・ワシが撃った。水ん中に落ちるだろ。この冷え込みだ、入る訳にもいかネェ。で、あれが拾いに行った。」。「オカミサンがですか?一体どうやって拾うんですか?」、「水に入らなきゃ拾えんだろう。下駄はかせたから大丈夫だ。」、「下駄って?」、「裸足じゃ怪我するだろうが・・・下駄を履かなきゃ入れん。ワシは下駄を履いてなかった。」、「ワタシ、行ってきます。」、「そうかい、頼むぜ。」私は月明かりを頼りに、休耕田の畦径を一の堤目指して急いだ。青い月明かりの下に黒々と陰の盛り上がる辺りが堤のある辺りだ。休耕田の稲の切り株には、早くも霜が輝いている。浅い池は岸辺の辺りから氷結し掛かっているかも知れない。私は自分の吐く真っ白な息の中に鼻先を突っ込みながら急いだ。池の外側の篠竹の藪の陰まで行き、呼吸を整えて耳を澄ます。藪の向こうの低い位置から、バシャンリー、バシャリーと弱い水音がする。その音は南に向かっていた。池の中に入るには水抜きの栓のある南側しかない。オカミサンはどうやら降りた所へ戻る処の様だ。私は栓口へと廻った。池の土手を上がり、藪の間から覗いて見ると、月光に輝く水面の波の中心に人影が見えた。オカミサンは片手に二羽のカモを持ち、もう一方の手で着物の裾を腰の辺り迠たくし上げている。ゆっくり、一歩一歩、下駄が抜けない様に水の中を此方へ向かって来る。「オカミサン、山口のオカミサン」。どうやら、自分が立てる水音のせいで聞こえないらしい。私は、その場を離れ、土手を下り、藪の向こうから大声を上げる。「オカミサア~ン、ヤマグチノ~!ワタシ、マチイチノ~、クニデ~ス。ムカ~イニキマシタァ!」。それから再び土手を上がり、水抜きのコンクリートを下りる。オカミサンは目の前だ。凍り付く様な水の中に腿まで浸かってやって来る。冷たさと寒さで足も動かない程の筈だ。片手にカモ、もう一方に着物の裾。「オカミサン、大丈夫ですか?」。私は思わずコンクリートの斜面を駆け降り、水辺の柔らかい砂泥に踝まで足を突っ込んで、そのまま水の中に飛び込みそうになる。「ナ、ニ、やってんだい。アブナイじゃないか。来るんじゃないヨ。」言葉の合間に歯の鳴る音がする。オカミサンは最後の力を振り絞って岸に上がり、ドサリとカモを落とした。一方の手は、まだ着物の裾をたくし上げたままだ。月明かりで青白く、濡れて光る腿がずっと上まで見えた。そして、その辺りに夜目にもそれと分かる独特の図柄が這い回っていた。
以下次号 |